News お知らせ・コラム
2025.07.11
コラム
【保育園・幼稚園の防犯カメラ導入ガイド】設置場所や補助金などの基礎知識もご紹介
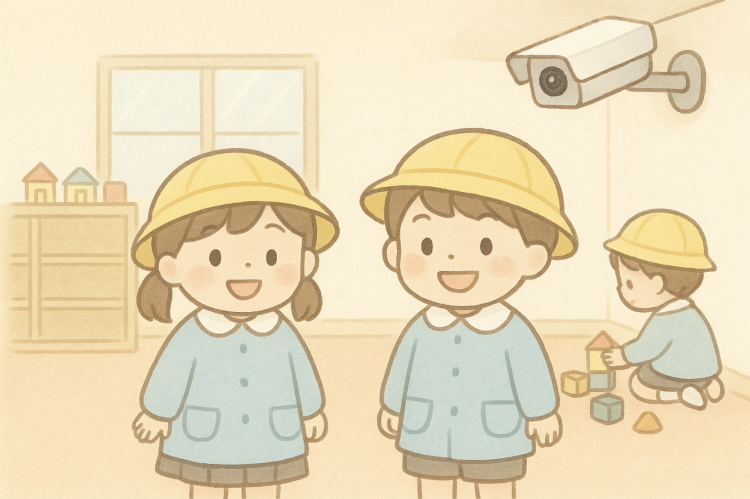
保育園や幼稚園に通う子どもたちは、まだ社会的にも身体的にもとても未熟な存在です。
そんな大切な命を預かる施設にとって、「安全で安心な環境づくり」は何よりも優先されるべき課題となっています。
近年では、不審者の侵入や送迎時のトラブル、園内での事故など、万が一の事態に備えた対策の一環として「防犯カメラの導入」を検討する園が増えています。
防犯カメラは単なる監視機器ではなく、園児を見守るもうひとつの目として、日々の保育における信頼と安心を支える存在です。
本記事では、保育施設における防犯カメラの必要性や設置のポイント、実際の運用方法、補助金制度の活用までをわかりやすく解説します。
| ・なぜ、防犯カメラが保育園や幼稚園に必要なのか? ・防犯カメラの設置場所とその効果 ・保育園・幼稚園の室内カメラ設置のメリットと注意点 ・カメラ導入時に確認すべき運用ルール ・防犯カメラ導入に活用できる補助金制度 ・まとめ |
なぜ、防犯カメラが保育園や幼稚園に必要なのか?
保育園や幼稚園では、小さな子どもたちが安心して過ごせる環境づくりが求められています。園内では思いがけないトラブルや外部からの危険が起こることもあり、より高い防犯意識が必要とされています。
そうした中で注目されているのが防犯カメラの導入です。
以前は大型施設や商業施設などに限定されていた設備でしたが、近年では保育施設にも広がりを見せています。
カメラの設置は、不審者の侵入防止といったセキュリティ対策だけでなく、園児の安全な見守り、トラブル時の状況確認、そして保護者への安心提供といった多面的な効果をもたらします。
特に共働き家庭が増える中、保護者の多くは「しっかり見守られているか」「何かあったときに園は適切に対応できるか」といった点を重視します。
園としても、防犯カメラを設置していることを説明会などで明示することで、園の安全対策をアピールでき、信頼の向上につながります。
また、防犯カメラは万が一のトラブルに備えた「記録装置」としても機能します。
客観的な証拠があることで、対応がスムーズになり、職員を守ることにもつながります。
このように、防犯カメラは園全体の安心・安全を支える大切な設備として、多くの保育現場で導入が進んでいるのです。
保育園・幼稚園の防犯カメラの設置場所とその効果

防犯カメラは「どこに設置するか」によって効果が大きく変わります。
保育園や幼稚園では、園児の安全だけでなく、保護者との接触の場や職員の働く環境も含めて、さまざまな場所でカメラの活用が期待されます。
ここでは、設置が効果的な代表的な場所と、その理由についてわかりやすく解説します。
園の出入口と門扉
園の出入口や門扉は、外部との接点となる重要な場所です。
ここに防犯カメラを設置することで、不審者の侵入を未然に防ぐ「抑止効果」が期待できます。
また、来園者の出入りを記録することで、トラブル発生時にも「誰が・いつ・どのように出入りしたか」を後から確認できます。
特に、無断での侵入やトラブルに発展した来客対応などの記録は、施設を守るうえで非常に有効です。
さらに、職員が常時入口を監視できない小規模園では、カメラによる自動録画や遠隔確認機能が安全管理を大きくサポートします。
駐車場・送迎エリア
登園・降園時は、保護者の車の出入りや人の往来が集中し、どうしても混雑しやすい時間帯です。
このタイミングで起こる接触事故や車のトラブルなども、防犯カメラがあれば記録に残せます。
また、駐車中の車両への接触や送迎時のマナーに関するクレームが発生した場合でも、映像をもとに冷静な対応が可能になります。
記録があることで保護者同士の誤解も避けやすくなり、園としての信頼性向上にもつながります。
加えて、送迎時間外に不審な車両の出入りがないかを確認するためのセキュリティ強化としても有効です。
死角になりやすい裏門・フェンスまわり
正門以外の出入口や建物裏手、フェンス沿いなどは、死角が生まれやすい場所です。
これらの箇所にカメラを設置していないと、外部からの侵入リスクが高まるだけでなく、職員や園児が意図せず危険に巻き込まれる可能性もあります。
死角になりがちな箇所にも適切にカメラを設置することで、園全体のセキュリティレベルを底上げすることができます。
また、カメラの角度や高さを調整することで、少ない台数でも広い範囲をカバーできるようになります。
このように、防犯カメラの設置場所は「目立つ場所」だけでなく、「見落とされがちな場所」への配慮も重要です。
園の構造や動線をふまえた設計が、より効果的な防犯につながります。
| 設置場所 | おすすめカメラの特徴 |
|---|---|
| 出入口・門 | バレット型カメラ(視認性が高く、抑止力がある) |
| 教室・廊下 | ドーム型カメラ(威圧感が少なく、目立ちにくい) |
| 駐車場・送迎エリア | 広角タイプやパンチルト式(角度調整ができる) |
| 死角や裏手 | 小型カメラ+赤外線対応(暗所に強い) |
保育園・幼稚園の室内カメラ設置のメリットと注意点
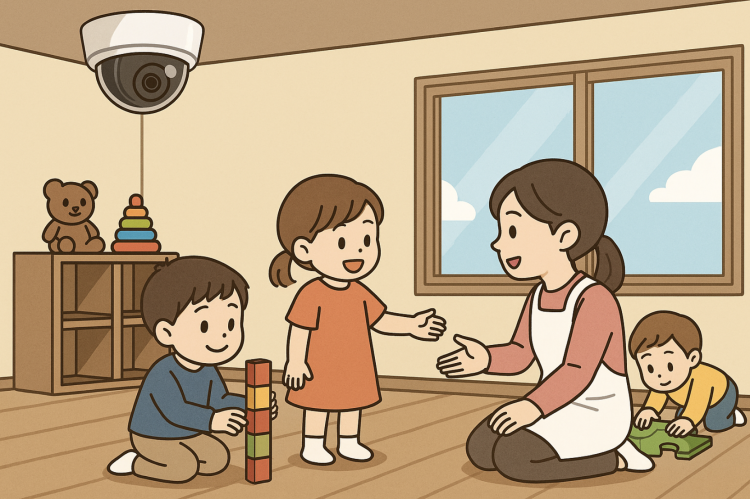
保育園や幼稚園では、防犯カメラを屋外だけでなく室内に設置するケースも増えています。
教室や廊下など園児が長時間過ごす場所に設置することで、安全管理だけでなく、保育の質を高める目的でも活用されています。
ただし、プライバシーへの配慮が欠かせないため、メリットと注意点をしっかり理解することが重要です。
室内設置のメリット
・トラブル時の客観的記録
園児同士のけんか、転倒、備品の破損など、職員がすべてを見届けるのが難しい場面でも、録画映像があれば事実確認ができます。
保護者への説明にも活用が可能です。
・保育の質向上
保育中のやり取りを録画することで、職員同士で指導方法の見直しや改善点の共有が可能になります。
新人職員の教育資料としても有用です。
・保護者の安心感向上
入園説明会や保護者面談で、防犯カメラの存在を伝えることにより、保護者にとっては「見守り体制が整っている」と感じられる安心材料になります。
・不正や事故の抑止
カメラが設置されていること自体が、意図的ないじめや不適切保育、備品の故意の破損などを防ぐ効果を持ちます。
室内設置の注意点
・プライバシーの確保
更衣スペースやトイレ周辺には絶対に設置しない、撮影範囲を限定する、レンズを目立たせないといった配慮が必要です。
・同意の取得
防犯カメラの設置については、保護者・職員双方への説明と同意が欠かせません。
設置の目的、保存期間、閲覧の条件などを明記した書面の配布が望ましいです。
・心理的負担への配慮
常時録画されることによる緊張感や萎縮を招かないよう、カメラの数・位置・サイズに注意し、「安心のための仕組み」として周知することが重要です。
・運用コスト
録画機材の導入費用やメンテナンス、データ保存にかかる費用など、導入後も継続的なコストが発生する点をあらかじめ計画に含めておく必要があります。
カメラ導入時に確認すべき運用ルール

防犯カメラを設置する際には、「設置すること」だけでなく、「どう使うか」「誰が管理するか」といった運用ルールの整備が非常に重要です。
保護者や職員との信頼関係を保ち、トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ確認しておきたいポイントをまとめました。
録画データの保存期間と管理方法
録画映像は、トラブル発生時の確認や証拠として非常に重要な資料になります。
ただし、保存期間が長すぎるとプライバシー侵害や管理コストの増加を招きます。
・ 一般的にデータの保存期間は「1週間〜1か月程度」が目安
・ 録画データは園のサーバーまたはクラウド上に安全に保管
・ アクセス制限(園長や責任者のみに限定)を設け、パスワードやアクセス履歴の管理を徹底
・ 定期的に保存先の容量や機器の点検も行うことでトラブルを未然に防ぐ
映像の閲覧・公開に関するルール
「誰が・いつ・どのような目的で映像を確認できるのか」を明確にしておくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。
・ 原則として園長やセキュリティ責任者のみが閲覧可能
・ 職員や保護者から閲覧依頼があった場合は、事前に書面で申請・理由を記載
・ SNSやブログなどへの無断転載・公開は禁止。職員間でも共有は必要最低限にとどめる
・ 閲覧記録を残しておくことで、不適切な利用を抑止する効果も
保護者・職員への事前説明と同意取得
防犯カメラはプライバシーに関わる設備であるため、保護者や職員からの理解と同意を得ることが非常に重要です。
・ 設置目的、録画範囲、保存期間、映像利用のルールなどを記載した説明書を配布
・ 必要に応じて保護者説明会を開催し、口頭でのフォローや質疑応答の時間を確保
・ 同意書の提出をもって導入の根拠とする。保管は厳重に行う。
トラブル発生時の対応フローを決めておく
防犯カメラの映像を確認した結果、園内のトラブルや職員の不適切な対応が発覚する場合もあります。
感情的にならず、スムーズな対応を行うためには、事前にフローを明文化しておくことが必要です。
・ トラブル発生時はまず責任者が映像を確認し、事実関係を整理
・ 職員対応:必要に応じて注意・再教育・保護者への報告など段階的に実施
・ 保護者対応:園長が一貫して担当し、事実確認・謝罪・再発防止策を丁寧に説明
・ 一連の対応経緯を記録し、内部共有することで再発防止と組織的な対応強化につながる
防犯カメラ導入に活用できる補助金制度
防犯カメラの導入は、設備費・設置工事費・録画機器など、ある程度まとまった初期費用がかかるため、保育園や幼稚園ではコスト面の不安を感じることも少なくありません。
そんなとき、園の負担を軽減しながら防犯強化が図れる手段として「補助金制度」の活用が挙げられます。
国や自治体では、子どもを守る安全対策の一環として、保育施設に対する設備投資を支援する補助金・助成金制度を用意している場合があります。
補助金・助成金制度を上手に活用することで、予算内で効果的な導入が実現可能です。
保育施設向けに活用できる主な補助金・助成制度
自治体や政府の一部補助金には、「地域の防犯対策」「子どもを守る施設整備事業」などの名目で、防犯カメラの設置を対象とするものがあります。
具体的には、以下のような制度が検討の対象になる可能性があります。
・ 自治体の防犯対策費補助金(市区町村単位で実施)
・ 内閣府や文部科学省が所管する「安心こども基金」や「施設整備等助成事業」
・ 私立幼稚園等に対する補助制度(都道府県が実施)
これらの制度は地域によって異なります。
また、定期的に金額や範囲などの見直しが入るので、必ず各自治体の公式サイトや担当窓口に確認することが重要です。
補助金を活用する際の注意点
補助金をスムーズに申請・活用するためには、以下のような点を事前に把握・準備しておくことが大切です。
・ 事前申請が必須
設置後に申請しても対象外となる場合が多いため、導入前に申請手続きを済ませる必要があります。
・ 対象経費の範囲を確認する
カメラ本体や設置費用だけでなく、保守契約・記録装置・設置に伴う電気工事などが補助対象となるか、事前にチェックが必要です。
・ 実績報告・書類管理
導入後に報告書や写真などを提出する必要がある場合もあります。業者とのやり取りも含めて、資料の整理を行いましょう。
補助金をうまく活用できれば、導入のハードルを下げつつ、より安全性の高い設備を整えることが可能です。
早めに情報収集を行い、準備を進めていきましょう。
まとめ
防犯カメラは、単なる機械的な監視装置ではなく、「園児の安全を守る」「職員の働きやすさを支える」「保護者の信頼を得る」といった、保育現場に必要不可欠な安心を支える基盤として定着しつつあります。
設置場所や映像の使い方、関係者への丁寧な説明など、導入には多くの配慮が求められますが、それらをしっかり整備することで、園全体の防犯意識と運営の透明性が高まります。
また、補助金制度などを活用することで、予算面の課題をクリアしながら、より高品質な設備導入も可能になります。
必要な準備と工夫を重ね、安全・安心の園づくりを進めていきましょう。
防犯カメラの設置は、未来の「もしも」に備えるだけでなく、日々の保育の質と信頼を高めるための第一歩となるでしょう。
キャトルプランでは、お客様の様々な問題に対して、最適な提案をいたします。
何かお困りごと等ございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
■カメラに関しまして(弊社HP URL)
防犯カメラ|(株)キャトルプラン|防犯カメラやゲートなどの防犯システムの専門商社 (quatre-plan.co.jp)
■導入事例に関しまして(弊社HP URL)
導入事例・お客様の声|(株)キャトルプラン|防犯カメラやゲートなどの防犯システムの専門商社 (quatre-plan.co.jp)
■初めての方に関しまして(弊社HP URL)
初めての方へ|(株)キャトルプラン|防犯カメラやゲートなどの防犯システムの専門商社 (quatre-plan.co.jp)
お問い合わせフォームはこちら
弊社情報や機器に関する情報は下記URLをご参照ください。
https://quatre-plan.co.jp/






